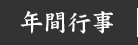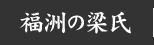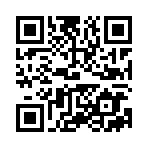2025年04月04日
令和7年度定時社員総会
2月28日(金)、梁氏倶楽部で定時社員総会が開催されました。出席した社員数は16名、委任状提出者が11名です。会の冒頭元祖を祀る祭壇に焼香、拝礼した後、総会議案の審議に入ります。


総会終了後、直ちに新役員による理事会が開かれ、代表理事の選定を行い、崎山健伸理事が再任されました。この後、会員の懇親会が開催され、終始和やかな雰囲気の会となりました。
文 事務局長 國吉薫



総会終了後、直ちに新役員による理事会が開かれ、代表理事の選定を行い、崎山健伸理事が再任されました。この後、会員の懇親会が開催され、終始和やかな雰囲気の会となりました。

文 事務局長 國吉薫
Posted by たんめー at
11:59
│Comments(0)
2025年03月27日
門中会員國吉俊秀さん宮古島文学賞受賞
梁氏呉江会会員の國吉俊秀さん(ペンネーム:国梓(くにし)としひで)さんが、去った2月7日(金)に発表された第8回宮古島文学賞で最高賞の一席に選ばれました。
今年の宮古島文学賞は「島」をテーマに全国から98編の応募で、その中から俊秀さんの「島の塔頭(タッチュウ)と電照菊」が最高賞に輝きました。俊秀さんはこれまでも第33回新沖縄文学賞、第53回農民文学賞を受賞し、地上文学賞、九州芸術祭文学賞の入賞の常連であり地元の同人誌「南涛文学」を中心に多くの作品を発表しています。創作活動の幅も広く小説をはじめ随筆、戯曲、児童文学、県内の文化講演会に出演されるなど活躍されています。また、2020年からは「南涛文学」を発刊している南涛文学会会長として地元の文筆家の育成にも尽力されています。
私はこれまで久米梁氏美術展に出展していただいた沖縄建設新聞社から出版された俊秀さんの小説「風に立つ石塔 風土建築家・清村勉伝」と「太陽(てぃだ)を染める城 首里城を蘇らせた職人たち」の貴重な挿絵原画を拝見して、挿絵作家の印象が強く、挿絵を手掛ける方という感想でした。しかし、今回の受賞で作家としての一面を見逃していたことに気づかされました。
今回の受賞作「島の塔頭(タッチュー)と電照菊」を読んでの感想は、俊秀さんの描かれる戦争の不条理と悲惨さをあらためて思い知らされるものでした。特に、作中に出てくる泰緬(たいめん)鉄道(死神鉄道)・インパール作戦とくればオールドシネマファンにとって名優早川雪州が出演した映画「戦場にかける橋」のリアルな心象風景を思い出します。今回の俊秀さんの受賞作は戦後80年を経て、戦世(いくさゆ)の記憶の風化という問題-沖縄でも祖父母や父母(沖縄線体験者)が重い口を開き語られる戦中・戦後の記憶-と相まって時宜を得た心に迫る作品だと思います。一読して俊秀さんの作家としての一面を再認識しました。
このように我が梁氏呉江会会員の中には才能に恵まれた方が数多くいらっしゃいます。今後も多才な人材の発掘、登用に力を入れなければという思いを強くしました。

資料2,俊秀さんの文学活動の軌跡(共著)

資料3,俊秀さんの既刊本紹介

私はこれまで久米梁氏美術展に出展していただいた沖縄建設新聞社から出版された俊秀さんの小説「風に立つ石塔 風土建築家・清村勉伝」と「太陽(てぃだ)を染める城 首里城を蘇らせた職人たち」の貴重な挿絵原画を拝見して、挿絵作家の印象が強く、挿絵を手掛ける方という感想でした。しかし、今回の受賞で作家としての一面を見逃していたことに気づかされました。
今回の受賞作「島の塔頭(タッチュー)と電照菊」を読んでの感想は、俊秀さんの描かれる戦争の不条理と悲惨さをあらためて思い知らされるものでした。特に、作中に出てくる泰緬(たいめん)鉄道(死神鉄道)・インパール作戦とくればオールドシネマファンにとって名優早川雪州が出演した映画「戦場にかける橋」のリアルな心象風景を思い出します。今回の俊秀さんの受賞作は戦後80年を経て、戦世(いくさゆ)の記憶の風化という問題-沖縄でも祖父母や父母(沖縄線体験者)が重い口を開き語られる戦中・戦後の記憶-と相まって時宜を得た心に迫る作品だと思います。一読して俊秀さんの作家としての一面を再認識しました。
このように我が梁氏呉江会会員の中には才能に恵まれた方が数多くいらっしゃいます。今後も多才な人材の発掘、登用に力を入れなければという思いを強くしました。
資料1,俊秀さんの文学活動の軌跡(同人誌「南涛文学」の掲載)

資料2,俊秀さんの文学活動の軌跡(共著)

資料3,俊秀さんの既刊本紹介

(文 崎山健伸)
2025年03月24日
福建と沖縄の交流会
日中交流イベント「福建沖縄文明対話」が3月15日、那覇市の八汐荘で開催されました。主催者で予てから梁氏と親交のある福建師範大学からの案内を受け、崎山会長など4人が参加しました。イベントは盛況で日中の関係者が会場を埋め尽くしていました。
始めに中国琉球史研究の中核を担った福建師範大学の「中琉関係研究所」の創立30周年を同大の謝必震名誉教授と琉大の赤嶺守名誉教授のくす玉割で祝いました。続く基調講演で琉大の上里賢一名誉教授は33年前に沖縄タイムス社が実施した福州から北京までの進貢使節のルートを辿る旅が、北京で留まったままだ。復路の旅を実現しようと提唱しました。北京から福州までの3,000キロを徒歩で戻る計画です。琉球王国時代の先人に想いを馳せるロマンに満ちた計画に梁氏からも、若者をぜひ参加させたいものです。
この日の目玉は福州大学人文社会科学学院音楽科の張暁娟教授の二胡と沖縄電電OB会の尺八、三味線のコラボでした。、特に張暁娟教授とお弟子さんによる三重奏の超絶技巧は見るのも聞くのも初めてと息を飲む驚きでした。
午後は中国沖縄の研究者の発表会が行われ、福建師範大学から福州市に昨年暮れ開館した中琉文化館の経緯を紹介していました。同館には梁氏会長の開館祝辞や梁氏家譜が展示されています。
始めに中国琉球史研究の中核を担った福建師範大学の「中琉関係研究所」の創立30周年を同大の謝必震名誉教授と琉大の赤嶺守名誉教授のくす玉割で祝いました。続く基調講演で琉大の上里賢一名誉教授は33年前に沖縄タイムス社が実施した福州から北京までの進貢使節のルートを辿る旅が、北京で留まったままだ。復路の旅を実現しようと提唱しました。北京から福州までの3,000キロを徒歩で戻る計画です。琉球王国時代の先人に想いを馳せるロマンに満ちた計画に梁氏からも、若者をぜひ参加させたいものです。
この日の目玉は福州大学人文社会科学学院音楽科の張暁娟教授の二胡と沖縄電電OB会の尺八、三味線のコラボでした。、特に張暁娟教授とお弟子さんによる三重奏の超絶技巧は見るのも聞くのも初めてと息を飲む驚きでした。
午後は中国沖縄の研究者の発表会が行われ、福建師範大学から福州市に昨年暮れ開館した中琉文化館の経緯を紹介していました。同館には梁氏会長の開館祝辞や梁氏家譜が展示されています。
梁氏の始祖は14世紀に福州から來琉し、末裔は大交易時代に出自である福建とのネットワークを駆使し琉球の発展に深い関わりを持ってきました。現代の梁氏にとって、これら福建・福州との関係を再認識し、日中の文化交流に資するのを確認するイベント参加でした。

上:張暁娟教授とお弟子さんによる二胡の演奏 下:梁氏呉江会一同との記念写真

上:張暁娟教授とお弟子さんによる二胡の演奏 下:梁氏呉江会一同との記念写真
(文 國吉 克哉)
2024年12月13日
福州へ行ってきました 3
大学での話を終えた翌日、福州国際空港に近い長楽区梅花鎮を訪ねました。
梅花鎮には琉球蔡氏の女性、蔡夫人を神とする廟がある事や、閩江の河口に位置し、進貢船が出入りした史実があって、琉球と中国の交流をテーマとする「長楽梅花中琉文化館」が造られました。その時代考証には福建師範大学が関わっていて、そのご縁もあり那覇市長から預かった「長楽梅花中琉文化館」への開館祝辞と梁氏呉江会崎山会長からの開館祝辞を、開館式直前の現地で福州市長楽区の区長へ届けました。
もう少し説明すると中琉文化館のある梅花鎮は中国との交易のため那覇を出港した進貢船が福州を目指して東シナ海を航海し、最初に目にする陸地で、目の前の閩江を遡れば福州城内へ到着します。また蔡夫人廟に名が残る琉球生まれの蔡夫人は織物の名手で皇帝に招かれ中国へ渡りましたが梅花鎮で亡くなり、神となって祀られています。梅花鎮の地域では今も神として広く信仰されて「琉球蔡夫人廟・琉球國蔡仙府・鶴上蔡氏夫人宮・新厝房祖庁」と4か所も廟があります。
今回、縁あって福建師範大学で話す機会があり、大学でも梅花鎮の蔡夫人廟でも中琉文化館でも、熱烈歓迎を受けました。互いの交流の歴史が沖縄へ中国文化をもたらし、我々県民の中に、祭祀や方言の一部として今も残り、互いに親近感が持ち合える故の大歓迎だと思います。久米三十六姓の末裔に生まれ、中国・琉球の交流の歴史を学び、そして伝える責務を再認識させる旅でした。

梅花鎮には琉球蔡氏の女性、蔡夫人を神とする廟がある事や、閩江の河口に位置し、進貢船が出入りした史実があって、琉球と中国の交流をテーマとする「長楽梅花中琉文化館」が造られました。その時代考証には福建師範大学が関わっていて、そのご縁もあり那覇市長から預かった「長楽梅花中琉文化館」への開館祝辞と梁氏呉江会崎山会長からの開館祝辞を、開館式直前の現地で福州市長楽区の区長へ届けました。
もう少し説明すると中琉文化館のある梅花鎮は中国との交易のため那覇を出港した進貢船が福州を目指して東シナ海を航海し、最初に目にする陸地で、目の前の閩江を遡れば福州城内へ到着します。また蔡夫人廟に名が残る琉球生まれの蔡夫人は織物の名手で皇帝に招かれ中国へ渡りましたが梅花鎮で亡くなり、神となって祀られています。梅花鎮の地域では今も神として広く信仰されて「琉球蔡夫人廟・琉球國蔡仙府・鶴上蔡氏夫人宮・新厝房祖庁」と4か所も廟があります。
今回、縁あって福建師範大学で話す機会があり、大学でも梅花鎮の蔡夫人廟でも中琉文化館でも、熱烈歓迎を受けました。互いの交流の歴史が沖縄へ中国文化をもたらし、我々県民の中に、祭祀や方言の一部として今も残り、互いに親近感が持ち合える故の大歓迎だと思います。久米三十六姓の末裔に生まれ、中国・琉球の交流の歴史を学び、そして伝える責務を再認識させる旅でした。

長楽梅花中琉文化館の入口 琉球國蔡仙府
文 國吉 克哉
2024年12月13日
福州へ行ってきました 2
講演会での話の導入として、閩人の末裔は久米三十六姓と称され明治の廃藩置県で実体を失った久米村に代わり、大正時代に久米崇聖会を設立し14世紀以来伝えて来た中国文化を継承していることを手短に紹介しました。
次に僕の伝えるべき今日の梁氏について話しました。琉球梁氏は現在の福州市長楽区呉航江田から渡来した「梁嵩」を始祖とする父系の血縁集団で、福建省各地に暮す梁氏とルーツを同じくする一族です。日々の暮らしや風習・方言にも中国の影響が残り、旧盆ではウチカビを燃やし、清明祭・ウマチーなどの祭祀行事と、年寄りを敬う敬老会、勉学に精進する若者を激励する学事奨励会を毎年開催しています。10年前には法人格のない梁氏門中を一般社団法人化して一族の財産を保全し子孫へ代々引き継ぐ仕組みを作りました。門中財産を運用し会員の相互扶助や結束に務め、親子レクや梁氏美術展の開催など新しい施策を試みています。中国や台湾の梁氏と交流して友好関係を築いている事も話しました。
福州市長楽区にルーツがある琉球梁氏だが、親戚がいるのではないかと会場へ問いかけると女子学生が手を挙げてくれました。残念ながら福建省生まれではなかったが、宋時代の宰相梁克家まで辿れば親戚だと連帯を伝えました。
仲本さんはお父さんが語っていた福州琉球館について話しました。
祖父英炤が琉球館で暮らしたのは明治末から大正の時代で、琉球館は既に本来の役目を終えて、乙商業学校で英語教師をしていた祖父や茶貿易商の儀間さんが住んでいました。祖父は福州時代の蒋介石と親交があり、東京の軍人養成学校へ留学する蒋介石を日本へ案内しました。台湾総統となった蒋介石は恩に報い、亡くなった祖父に代わり息子夫婦を戦後台湾へ招待しています。後に祖父は福州を離れ那覇の商業学校で支那語の先生になります。琉球歴史の至宝である「歴代宝案」を久米の旧家で発見したのはその頃です。
講演後の質疑では琉球館を語る生き証人が現れ驚きとか、花米は中国由来か、梁氏以外でも習慣があるのかとか、呉江会の名前の意味など聞かれ、我々の話が何かの役に立ったようでホットしました。
(参考)歴代宝案は琉球王府400年余の外交文書を収録しています。門外不出とされ久米村内に秘匿していたが、発見と県立図書館への移管により世に出ました。
図書館への移管を推進した1人が梁氏の國吉有慶です。「もし発見が無ければ、もし移管がなければ」歴代宝案は写本を残さずに、十十空襲で焼けていたのです。

次に僕の伝えるべき今日の梁氏について話しました。琉球梁氏は現在の福州市長楽区呉航江田から渡来した「梁嵩」を始祖とする父系の血縁集団で、福建省各地に暮す梁氏とルーツを同じくする一族です。日々の暮らしや風習・方言にも中国の影響が残り、旧盆ではウチカビを燃やし、清明祭・ウマチーなどの祭祀行事と、年寄りを敬う敬老会、勉学に精進する若者を激励する学事奨励会を毎年開催しています。10年前には法人格のない梁氏門中を一般社団法人化して一族の財産を保全し子孫へ代々引き継ぐ仕組みを作りました。門中財産を運用し会員の相互扶助や結束に務め、親子レクや梁氏美術展の開催など新しい施策を試みています。中国や台湾の梁氏と交流して友好関係を築いている事も話しました。
福州市長楽区にルーツがある琉球梁氏だが、親戚がいるのではないかと会場へ問いかけると女子学生が手を挙げてくれました。残念ながら福建省生まれではなかったが、宋時代の宰相梁克家まで辿れば親戚だと連帯を伝えました。
仲本さんはお父さんが語っていた福州琉球館について話しました。
祖父英炤が琉球館で暮らしたのは明治末から大正の時代で、琉球館は既に本来の役目を終えて、乙商業学校で英語教師をしていた祖父や茶貿易商の儀間さんが住んでいました。祖父は福州時代の蒋介石と親交があり、東京の軍人養成学校へ留学する蒋介石を日本へ案内しました。台湾総統となった蒋介石は恩に報い、亡くなった祖父に代わり息子夫婦を戦後台湾へ招待しています。後に祖父は福州を離れ那覇の商業学校で支那語の先生になります。琉球歴史の至宝である「歴代宝案」を久米の旧家で発見したのはその頃です。
講演後の質疑では琉球館を語る生き証人が現れ驚きとか、花米は中国由来か、梁氏以外でも習慣があるのかとか、呉江会の名前の意味など聞かれ、我々の話が何かの役に立ったようでホットしました。
(参考)歴代宝案は琉球王府400年余の外交文書を収録しています。門外不出とされ久米村内に秘匿していたが、発見と県立図書館への移管により世に出ました。
図書館への移管を推進した1人が梁氏の國吉有慶です。「もし発見が無ければ、もし移管がなければ」歴代宝案は写本を残さずに、十十空襲で焼けていたのです。

講演会の様子 1 講演会の様子 2
文 國吉 克哉
2024年12月13日
福州へ行ってきました 1
中国と琉球の交流の歴史については中国・台湾・沖縄の大学で「中琉歴史関係国際学術会議」が組織され研究されています。中国・台湾の大学から研究者が沖縄を訪れる事があり、今年8月には福建師範大学の大学院生一行が梁氏呉江会を訪れています。この逆の話があって、中国人の末裔である久米三十六姓当事者の目線で話を聞かせてくれと、声が掛かり、久米崇聖会の理事長を共に務めた陳氏の仲本さんと僕が、令和6年10月に福建師範大学で久米三十六姓について話をすることになりました。
福建師範大学は福建省の省都福州市にあり県人が福州へ行くと一度は訪れる琉球人墓に近い旗山区に大学があります。学生数5万人、キャンパス内の移動は自転車や車だろうかと心配するほど広大でした。大学にはベトナムやタイなど東南アジアと中国の交流の歴史を研究する研究所があり、その一つに「中琉関係研究所」があって14世紀頃に始まる中国と琉球の交流の歴史、久米三十六姓の事績などの研究拠点となっています。
我々の講演会場は中琉関係研究所のあるビル2階の大教室で、既に70人余が待っていました。研究所所長の頼正維教授をトップに中国琉球の交流史研究者そして大学院や学部の学生達です。そんな会場で話の持ち時間は各1時間半でした。

福建師範大学は福建省の省都福州市にあり県人が福州へ行くと一度は訪れる琉球人墓に近い旗山区に大学があります。学生数5万人、キャンパス内の移動は自転車や車だろうかと心配するほど広大でした。大学にはベトナムやタイなど東南アジアと中国の交流の歴史を研究する研究所があり、その一つに「中琉関係研究所」があって14世紀頃に始まる中国と琉球の交流の歴史、久米三十六姓の事績などの研究拠点となっています。
我々の講演会場は中琉関係研究所のあるビル2階の大教室で、既に70人余が待っていました。研究所所長の頼正維教授をトップに中国琉球の交流史研究者そして大学院や学部の学生達です。そんな会場で話の持ち時間は各1時間半でした。

講演会開催の学内告知(電子版) 頼正維教授へ「梁氏便り」等の資料贈呈
文 國吉 克哉
2024年10月29日
福建師範大学一行の久米梁氏呉江会訪問

事務所にて福建師範大学中琉関係研究所一行との交流
8月19日福建師範大学中琉関係研究所陳碩炫准教授や大学院生が琉球経済戦略研究会の方徳輝理事長とともに久米梁氏呉江会を訪れました。一行は全員が博士もしくは博士課程で勉強中のそうそうたるメンバーで、半分の人が日本語を話せました。
大学の夏休みを利用して福州市から来県し、中国と琉球の交流史調査研究のため10日間ほどの滞在です。琉大や県立博物館での文献調査、首里城周辺の史跡や梁氏・毛氏などの現地調査を行っています。
呉江会事務所では清明祭・ウマチーなどの祭祀行事、敬老会・学事奨励会・梁氏美術展などの活動について説明しました。
次に「大宗梁氏・小宗崎山家・小宗古謝家」の家譜3点と福建梁氏の「梁氏族譜」を広げて話を進め、琉球梁氏と福建梁氏は宋時代の状元梁克家に繋がるのだと話が弾みました。また家譜の表装が中国風の絹緞子である事や金箔による訂正、そして屋取や海外県外進出による子孫の広がりにまで話題になりました。
話題が白熱したのは系図座で押され家譜に残る「首里之印」そして、割印として使用されている「系記封印」と掠入を防ぐために押された「系紀之印」でした。しかし呉江会にある家譜写しでは「系記封印」と「系紀之印」が不鮮明で印影の読み取りが十分にできませんでした。
後日、古謝昇さんが那覇市歴史博物館から鮮明な印影の「東氏久手堅家譜」の写を入手しこれを陳碩炫准教授へ照会しました。難解な2種類の印影は「系記封印」と「系紀之印」と彫られているとの回答で、「系記」と「系紀」は同じ読みなのに、何故に1文字異なるのかもっと調べたいと付け加えています。この調査結果も楽しみです。

梁氏倶楽部見学
呉江会事務所での説明意見交換の後、祭祀行事や学事奨励会・定時総会が行われる梁氏倶楽部へ移動し、元祖「梁嵩」に拝礼しました。祭壇には戦前の久米三十六姓のどこの家の仏壇にもあった対聯を掲げたと紹介し、学事奨励会用の対句「梁氏祖廟満祥気」「孫子修学翔四海」と、通常用の「江田發祖廣文教」「球陽敷徳榮千年」の対句がリバーシブルに造られていると説明しました。また2011年に梁氏倶楽部の建物を大修理したとき、「1954年11月23日上棟式」と書かれた「紫微鑾駕」が現れたと話すと、対聯もこれも中国由来の文化だと、皆さん喜んでくれました。歴代会長の写真や扁額を見てもらい、福建師範大学一行の現地調査を終えました。
文 國吉 克哉
2024年10月21日
第7回 久米梁氏美術展の開催
今年もパレットくもじ6階那覇市民ギャラリー第3展示室において10月1日(火)から6日(日)まで第7回 久米梁氏美術展を開催し、6日間の期間中、参観者は296名の来場がありました。
9月22日の作品の申し込み締め切りに間に合った出展数は15点で展示が心配されましたが9月30日作品搬入当日には45点がそろい例年並みの出展数となりました。
内訳は絵画14点、写真10点、工芸18点、書3点、出展者数は29名です。部門別では去年に比べ写真部門が減少し、絵画・工芸部門が増加しました。工芸作品の増加に伴い会場のレイアウトが複雑となりましたが美術展準備委会委員長國吉 健郎さんの活躍で素晴らしい展示が出来ました。

また、今年は出展規約変更後初の美術展です。去年の反省を踏まえ参観者の質問になるべく答えられるよう出展申込書に撮影・作画場所と作品意図・説明をあらかじめ記入してもらいました。記入提出された作品ではスムーズな受け答えができましたが、申込書の提出は半数にとどまり今後記入の徹底をはかりたいと思います。

今年出展数が増加した工芸部門は、門中の皆さんの趣味をいかした多彩な作品が並び参観者の目を楽しませていました。

毎回好評なキッズコーナーと親子体験レクリエーションのサンゴ染め作品は今年も10作品の出展があり定着してきています。それにしても毎回子供たちの才能には驚かされています。
また、参観者から「他には見られない催しなので是非続けて欲しい」との励ましの声をいただきました。
今年も門中の皆さん、準備委員会・理事の皆さんには物心両面よりご協力を頂き無事閉会となりました。あらためて深謝致します。
9月22日の作品の申し込み締め切りに間に合った出展数は15点で展示が心配されましたが9月30日作品搬入当日には45点がそろい例年並みの出展数となりました。
内訳は絵画14点、写真10点、工芸18点、書3点、出展者数は29名です。部門別では去年に比べ写真部門が減少し、絵画・工芸部門が増加しました。工芸作品の増加に伴い会場のレイアウトが複雑となりましたが美術展準備委会委員長國吉 健郎さんの活躍で素晴らしい展示が出来ました。

第7回 久米梁氏美術展会場風景
また、今年は出展規約変更後初の美術展です。去年の反省を踏まえ参観者の質問になるべく答えられるよう出展申込書に撮影・作画場所と作品意図・説明をあらかじめ記入してもらいました。記入提出された作品ではスムーズな受け答えができましたが、申込書の提出は半数にとどまり今後記入の徹底をはかりたいと思います。

工芸部門の躍進
今年出展数が増加した工芸部門は、門中の皆さんの趣味をいかした多彩な作品が並び参観者の目を楽しませていました。

キッズコーナー・親子レク作品の定着
毎回好評なキッズコーナーと親子体験レクリエーションのサンゴ染め作品は今年も10作品の出展があり定着してきています。それにしても毎回子供たちの才能には驚かされています。
また、参観者から「他には見られない催しなので是非続けて欲しい」との励ましの声をいただきました。
今年も門中の皆さん、準備委員会・理事の皆さんには物心両面よりご協力を頂き無事閉会となりました。あらためて深謝致します。
文 崎山 健伸
2024年10月21日
令和6年度夏休み親子レク「サンゴ染め体験」
令和6年8月11日(日)に門中交流事業として、夏休み親子レクリエーションを実施しました。昨年度の「紅型」体験が大変好評でしたので、今年の親子レクも伝統工芸体験とし、那覇市首里山川町にある「首里琉染」の工房にて「サンゴ染め」を体験してきました。
首里琉染は染織作家の山岡古都(やまおかこと)氏が紅型の復興と染色技術の発展・伝承を目的に創立した工房で、琉球王国時代の王都首里の第一坊門であった「中山門」跡地という由緒ある場所に建っています。建物自体は飛騨高山から移築した合掌造りの古民家で、沖縄ではめずらしい切妻屋根と格子窓が首里の街並みに自然とマッチしています。1階は展示場とショップ、2階が体験工房、3階が職人工房となっています。
サンゴ染めとは、化石になったサンゴの断面を土台に、その上に生地を載せ、染料を使い拓本を取る染技法です。サンゴには満月の夜にたくさん産卵することから「子孫繁栄」、そして長い年月をかけて成長することから「長寿」の意味合いがあるとのことです。

今回の親子レクには、子供8名、保護者7名の計15名、5家族が参加しました。
サンゴ染め体験の所要時間は約50分で、Tシャツ、トートバック、ふろしき、手ぬぐいから好みのアイテムを選び染めていきます。大小さまざまなサンゴの化石からデザインを組み合わせ、タンポと呼ばれる染道具に赤・青・黄・紫の4色の染料を含ませて、生地をこすりながら染め上げていきます。用いられる染料は、木の皮や実、草の根などをたたき出して作ったオリジナルの植物染料です。
黄+青=緑、黄+紫=茶など、色を混ぜ合わせることでたくさんの色合いを出すことができます。

工房スタッフの丁寧な説明の後、いよいよ染め体験がスタートです。
染料を2、3滴パレットに垂らし、好みの色をつくりあげたらタンポに染料を含ませていきます。そして、このタンポをサンゴの土台にセッティングした生地に擦り付けると綺麗なサンゴ模様が生地にくっきり浮かび上がってきます。
一度始まれば、子供も大人も皆真剣です。真っ白な生地に己の美的感性で染め上げていく作業に全員が夢中になっています。大きなサンゴを使って大胆に中央から色付けしていく者、端から小さく丁寧に色付けしていく者、多くの色のグラデーションで色付けをしていく者など、まさに十人十色といった情景です。

あっという間に約50分の体験作業が終わり作品の完成です。工房スタッフの上手な指導もあり、皆素晴らしい出来栄えです。工房内で親子の作品を比べながら記念撮影してサンゴ染め体験を終了しました。作品は持ち帰り、あて布の上からアイロンをかけると染料が定着して完全に仕上がります。夏休みの自由研究の宿題として学校に提出した後に、梁氏美術展に出展してもらえたら幸いです。
サンゴ染め体験後は、3階の職人工房を見学させていただきました。工房スタッフには、体験の受付から染め指導、工房見学と丁寧に対応していただき、とても感謝しています。

楽しくサンゴ染めを体験した後は、近くのイタリアンレストランでランチをいただきました。那覇の街並みを一望できるテラス席を貸し切り、門中一同でランチ会です。美味しいパスタ料理と綺麗な景色も相まって、子供同士、保護者同士で楽しく会話が盛り上がり、あっという間にランチタイムは終了しました。
これをもって今年の親子レクリエーションは終了し、各自解散しました。参加者からは大変ご好評をいただきましたので、来年の親子レクリエーションについても、内容を吟味してまいりたいと考えています。

首里琉染は染織作家の山岡古都(やまおかこと)氏が紅型の復興と染色技術の発展・伝承を目的に創立した工房で、琉球王国時代の王都首里の第一坊門であった「中山門」跡地という由緒ある場所に建っています。建物自体は飛騨高山から移築した合掌造りの古民家で、沖縄ではめずらしい切妻屋根と格子窓が首里の街並みに自然とマッチしています。1階は展示場とショップ、2階が体験工房、3階が職人工房となっています。
サンゴ染めとは、化石になったサンゴの断面を土台に、その上に生地を載せ、染料を使い拓本を取る染技法です。サンゴには満月の夜にたくさん産卵することから「子孫繁栄」、そして長い年月をかけて成長することから「長寿」の意味合いがあるとのことです。

改装中の「首里琉染」と工房内部
今回の親子レクには、子供8名、保護者7名の計15名、5家族が参加しました。
サンゴ染め体験の所要時間は約50分で、Tシャツ、トートバック、ふろしき、手ぬぐいから好みのアイテムを選び染めていきます。大小さまざまなサンゴの化石からデザインを組み合わせ、タンポと呼ばれる染道具に赤・青・黄・紫の4色の染料を含ませて、生地をこすりながら染め上げていきます。用いられる染料は、木の皮や実、草の根などをたたき出して作ったオリジナルの植物染料です。
黄+青=緑、黄+紫=茶など、色を混ぜ合わせることでたくさんの色合いを出すことができます。

「サンゴ染め」に用いた染料・染料材料・混色見本・スタンプ・サンゴ台
工房スタッフの丁寧な説明の後、いよいよ染め体験がスタートです。
染料を2、3滴パレットに垂らし、好みの色をつくりあげたらタンポに染料を含ませていきます。そして、このタンポをサンゴの土台にセッティングした生地に擦り付けると綺麗なサンゴ模様が生地にくっきり浮かび上がってきます。
一度始まれば、子供も大人も皆真剣です。真っ白な生地に己の美的感性で染め上げていく作業に全員が夢中になっています。大きなサンゴを使って大胆に中央から色付けしていく者、端から小さく丁寧に色付けしていく者、多くの色のグラデーションで色付けをしていく者など、まさに十人十色といった情景です。

思案中の「サンゴ染め体験」の皆さん
あっという間に約50分の体験作業が終わり作品の完成です。工房スタッフの上手な指導もあり、皆素晴らしい出来栄えです。工房内で親子の作品を比べながら記念撮影してサンゴ染め体験を終了しました。作品は持ち帰り、あて布の上からアイロンをかけると染料が定着して完全に仕上がります。夏休みの自由研究の宿題として学校に提出した後に、梁氏美術展に出展してもらえたら幸いです。
サンゴ染め体験後は、3階の職人工房を見学させていただきました。工房スタッフには、体験の受付から染め指導、工房見学と丁寧に対応していただき、とても感謝しています。

参加家族のいろいろな素材を使った「サンゴ染め」作品(大変良くできました )
)
 )
)楽しくサンゴ染めを体験した後は、近くのイタリアンレストランでランチをいただきました。那覇の街並みを一望できるテラス席を貸し切り、門中一同でランチ会です。美味しいパスタ料理と綺麗な景色も相まって、子供同士、保護者同士で楽しく会話が盛り上がり、あっという間にランチタイムは終了しました。
これをもって今年の親子レクリエーションは終了し、各自解散しました。参加者からは大変ご好評をいただきましたので、来年の親子レクリエーションについても、内容を吟味してまいりたいと考えています。

親子レク終了後の楽しいランチタイムの一コマ
文 崎山春樹
2024年09月20日
令和6年度梁氏門中敬老会
まだまだ夏の暑さが残る9月8日(日)、「梁氏門中敬老会」がパシフィックホテル沖縄で開催されました。令和2年に新型コロナの感染流行のため、敬老会が中止となって以来、5年振りの敬老会です。

今年は梁氏73歳以上の長寿者(那覇近郊在住)は男性43人、女性47人の合計90人で、令和元年より9人多くなりました。長寿者(73歳)の仲間入りをしたのは男性3人、女性3人です。長寿者の最高齢は、男性が91歳、女性が98歳となりました。当日ご出席された長寿者は46人で、代理や付き添い等も合わせて60人の出席となり賑やかな祝宴となりました。
幕開けでは、始めに古典音楽安冨祖弦声会、玉城正治研究所の大城竹秀師範ら5名による重厚な三線と味わい深い歌声に乗せて、玉城流翔節会の国吉安子、国吉真由美さんによる優雅な舞“かぎやで風”が華を添えます。続いて辺野古節、御縁節と縁起のいい演奏で会が始まりました。
崎山会長の挨拶ではご長寿の皆さんへのお祝いのことばがあり、続いて國吉保武呉江会顧問の乾杯の音頭で会食が始まり、美味しいご馳走を囲みながら交流を深めました。
敬老会では恒例となっている余興タイムがありますが、今年の余興は例年とは違い、舞踊、歌手のプロによる出演で、見ごたえのあるショーとなりました。始めに玉城流翔節会、国吉安子さんが、地唄三線の軽快なテンポに乗せて“鳩間節”を舞い、祝宴の気分を盛り立てました。
次に登場したのは、地元を拠点に国内・海外にて活躍しているシンガーソングライター&ミュージシャンのCOJACO & KAWORUさん夫妻です。三線とエレキギターの伴奏でオリジナル曲の“ウムイウタ”、オリオンビールのCMソング“一番さくら”、カバー曲の“涙そうそう”など、透き通った美しい声で会場を魅了しました。
COJACOは芸名ですが、COJACOさんの本名(旧姓)は古謝貴子と言い、長寿祝いで出席されている古謝初子さんの娘さんなのです。母親の長寿を祝って、ボランテイアで出演してくれました。
余興の最後は、前段で優雅な舞を見せた国吉安子さんが、一転してハーメー(お婆ちゃん)に変装して、沖縄漫談の開祖として有名な小那覇舞天の塩屋(スーヤー)のパーパーをコミカルに演じました。

余興の後は、亀島伸昭呉江会副会長から、5年振りに敬老会を再開でき皆様にお会いできて大変嬉しい、これからも体調管理に気を付けて、いつまでもお元気でいて下さいとお祝いの言葉がありました。この後、会長から出席者41名の長寿者へ直接お祝い金の贈呈が行われました。

次は恒例のカラオケタイムです。多くの長寿者が自慢の歌声をマイクに乗せて楽しみました。最後に崎山孝次郎呉江会顧問から長寿者を代表して愉快な謝辞があり、今年の敬老会は終了となりました。

事務局長 国吉 薫
写真 國吉健郎(呉江会監事)

今年は梁氏73歳以上の長寿者(那覇近郊在住)は男性43人、女性47人の合計90人で、令和元年より9人多くなりました。長寿者(73歳)の仲間入りをしたのは男性3人、女性3人です。長寿者の最高齢は、男性が91歳、女性が98歳となりました。当日ご出席された長寿者は46人で、代理や付き添い等も合わせて60人の出席となり賑やかな祝宴となりました。
幕開けでは、始めに古典音楽安冨祖弦声会、玉城正治研究所の大城竹秀師範ら5名による重厚な三線と味わい深い歌声に乗せて、玉城流翔節会の国吉安子、国吉真由美さんによる優雅な舞“かぎやで風”が華を添えます。続いて辺野古節、御縁節と縁起のいい演奏で会が始まりました。

崎山会長の挨拶ではご長寿の皆さんへのお祝いのことばがあり、続いて國吉保武呉江会顧問の乾杯の音頭で会食が始まり、美味しいご馳走を囲みながら交流を深めました。

敬老会では恒例となっている余興タイムがありますが、今年の余興は例年とは違い、舞踊、歌手のプロによる出演で、見ごたえのあるショーとなりました。始めに玉城流翔節会、国吉安子さんが、地唄三線の軽快なテンポに乗せて“鳩間節”を舞い、祝宴の気分を盛り立てました。
次に登場したのは、地元を拠点に国内・海外にて活躍しているシンガーソングライター&ミュージシャンのCOJACO & KAWORUさん夫妻です。三線とエレキギターの伴奏でオリジナル曲の“ウムイウタ”、オリオンビールのCMソング“一番さくら”、カバー曲の“涙そうそう”など、透き通った美しい声で会場を魅了しました。

COJACOは芸名ですが、COJACOさんの本名(旧姓)は古謝貴子と言い、長寿祝いで出席されている古謝初子さんの娘さんなのです。母親の長寿を祝って、ボランテイアで出演してくれました。
余興の最後は、前段で優雅な舞を見せた国吉安子さんが、一転してハーメー(お婆ちゃん)に変装して、沖縄漫談の開祖として有名な小那覇舞天の塩屋(スーヤー)のパーパーをコミカルに演じました。

余興の後は、亀島伸昭呉江会副会長から、5年振りに敬老会を再開でき皆様にお会いできて大変嬉しい、これからも体調管理に気を付けて、いつまでもお元気でいて下さいとお祝いの言葉がありました。この後、会長から出席者41名の長寿者へ直接お祝い金の贈呈が行われました。


次は恒例のカラオケタイムです。多くの長寿者が自慢の歌声をマイクに乗せて楽しみました。最後に崎山孝次郎呉江会顧問から長寿者を代表して愉快な謝辞があり、今年の敬老会は終了となりました。


事務局長 国吉 薫
写真 國吉健郎(呉江会監事)
2024年05月22日
台湾の梁氏訪ねて3泊4日の旅
令和5年11月に台湾の彰化縣梁姓宗親会親善訪問に参加した梁氏呉江会理事の上津敏さんが、旅行記を寄稿しましたので掲載します。
「 11月15日台湾へ旅立った。那覇から1時間40分で台北の桃園空港へ到着し、「鹿港龍山寺」「鹿港天后宮」「鹿港老街」を見学し、台湾の梁氏を訪ねて彰化縣梁姓宗親会」を訪問、歓迎晩餐会が行われた。お互いの挨拶の後、豪華な料理が運ばれ和やかな雰囲気で夕食会が始まった。熱烈歓迎を受けて同族の強い絆を感じた。
今後もよろしくお願いしますと別れを告げ、1日目の日程は終了した。


2日目は専用車にて九族文化村見学へ向かった。文化村は台湾原住民に関するテーマパークで原住民の建築物や文物が展示されており、九族広場では各部族の歌と踊りのショウが見学できた。動きの速い独特な踊りに感激した。その後、「鼎泰豊」にて夕食をすませホテルへ戻った。

3日目はレストランにて朝食後、故宮博物館の見学に向かった。素晴らしい宝物を堪能し終えて、台北101にて夕食を済ませ台北の夜市見学へ向かった。台北101は日本の熊谷組が建設したそうで、観光地になっている。
台北の地下鉄は鹿島建設が建設したそうである。台湾のインフラ整備には日本の技術が貢献したことに誇りを感じた。これからも台湾とは仲良くしたいものである。
4日目は午前中「台北龍山寺」「剥皮寮」「紅楼」を見学し昼食後、桃園国際空港へ向かった。全日程を終え、6時に無事那覇へ到着した。楽しかった旅行。感謝、後會有期、再見。 」
上津 敏
「 11月15日台湾へ旅立った。那覇から1時間40分で台北の桃園空港へ到着し、「鹿港龍山寺」「鹿港天后宮」「鹿港老街」を見学し、台湾の梁氏を訪ねて彰化縣梁姓宗親会」を訪問、歓迎晩餐会が行われた。お互いの挨拶の後、豪華な料理が運ばれ和やかな雰囲気で夕食会が始まった。熱烈歓迎を受けて同族の強い絆を感じた。
今後もよろしくお願いしますと別れを告げ、1日目の日程は終了した。



2日目は専用車にて九族文化村見学へ向かった。文化村は台湾原住民に関するテーマパークで原住民の建築物や文物が展示されており、九族広場では各部族の歌と踊りのショウが見学できた。動きの速い独特な踊りに感激した。その後、「鼎泰豊」にて夕食をすませホテルへ戻った。


3日目はレストランにて朝食後、故宮博物館の見学に向かった。素晴らしい宝物を堪能し終えて、台北101にて夕食を済ませ台北の夜市見学へ向かった。台北101は日本の熊谷組が建設したそうで、観光地になっている。
台北の地下鉄は鹿島建設が建設したそうである。台湾のインフラ整備には日本の技術が貢献したことに誇りを感じた。これからも台湾とは仲良くしたいものである。

4日目は午前中「台北龍山寺」「剥皮寮」「紅楼」を見学し昼食後、桃園国際空港へ向かった。全日程を終え、6時に無事那覇へ到着した。楽しかった旅行。感謝、後會有期、再見。 」
上津 敏
2024年05月21日
気分転換の台湾旅行
令和5年11月に台湾の彰化縣梁姓宗親会親善訪問に参加した梁氏門中の古謝昇さんが、旅行記を寄稿しましたので掲載します。
「 令和5年11月15日 早朝5時30分頃那覇国際空港に到着した。既に國吉和男団長をはじめ、4,5人の門中仲間が来ていた。
東亜旅行社の社長と女性社員が台湾行きの渡航手続きをしていたが、自分は着くなり女性社員からパスポートの提示等を求められた。
しばらくして、その方から私に皆さんは得しているね。このスケジュールでは3泊4日の予定だが、実質は4泊5日と同じですよと言われた。
何故なら、朝一番で行くから、1時間の時差の関係で向こうには早く着くしその日有効に使える、思いどおりに行動できます。楽しんで下さい、と。
こんなことは台湾旅行で何回も経験して分かってはいるが、旅行社の方から直接こんな事を言われると、何となく嬉しくなった。実は、その日の新聞ではプロ野球ドラフト会議で楽天から一位指名されていた私の甥の次男(古謝 樹)が、契約金1億円、年棒1600万円を提示されたニュースが掲載されていたこともあって、まさかこんな大金が入るとは思いながら、これは現実だと自分のことのように朝からルンルン気分であった。そういう自分なりの吉兆のなかでの台湾旅行は心ウキウキしていたのを覚えている。

さて、久米梁氏呉江会主催の台湾旅行は、私にとって10年ぶりであるが、応募者も8名の少人数ではあったが、皆門中員ということで、実に楽しく、ザックバランに打ち解けた雰囲気であった。
新型コロナの規制が緩和されて海外渡航もある程度、自由に行き来できることは、後期高齢の者にとっては今までの閉塞感からの開放、ストレス解消とか気分転換には一番薬になるとの思いで、喜んで応募したことを覚えている。
今回の主な台湾旅行は、台湾彰化県の同じ梁氏のルーツを持つといわれる人々(中国福建からの渡来のいわゆる漢民族の末裔)で組織する社団法人彰化縣梁姓宗親会への親善訪問ということであったが、その組織自体の設立目的として、先祖の徳を継承し、親孝行と兄弟愛を実践。氏族間の団結を追求し、相互扶助、協力、倫理と道徳を促進する等、おおよそ日本の戦前の道徳教育を彷彿させる定款内容である。
いずれにしても、台湾梁氏一族との夜の交流会(約30人程)では大変な持てなしを受けたが、沖縄の亀島、古謝、國吉、上江洲等の苗字ではなく、オール梁氏の名称であり、国柄からして当然ではあるが、ちょっと違和感があった。ただ、食べたり、飲んだりするうちに彼らの顔つきを良く見ると、我々の顔つきと似ていたのは考えすぎかな。
その中でも宗親会の理事長は、台湾では有数のコンピューター電子周辺機器の製造メーカーの会長として活躍中であり、その統率力とか人柄のよさ等いい印象を持ったのは皆、同じだと思います。
「 令和5年11月15日 早朝5時30分頃那覇国際空港に到着した。既に國吉和男団長をはじめ、4,5人の門中仲間が来ていた。
東亜旅行社の社長と女性社員が台湾行きの渡航手続きをしていたが、自分は着くなり女性社員からパスポートの提示等を求められた。
しばらくして、その方から私に皆さんは得しているね。このスケジュールでは3泊4日の予定だが、実質は4泊5日と同じですよと言われた。
何故なら、朝一番で行くから、1時間の時差の関係で向こうには早く着くしその日有効に使える、思いどおりに行動できます。楽しんで下さい、と。
こんなことは台湾旅行で何回も経験して分かってはいるが、旅行社の方から直接こんな事を言われると、何となく嬉しくなった。実は、その日の新聞ではプロ野球ドラフト会議で楽天から一位指名されていた私の甥の次男(古謝 樹)が、契約金1億円、年棒1600万円を提示されたニュースが掲載されていたこともあって、まさかこんな大金が入るとは思いながら、これは現実だと自分のことのように朝からルンルン気分であった。そういう自分なりの吉兆のなかでの台湾旅行は心ウキウキしていたのを覚えている。


さて、久米梁氏呉江会主催の台湾旅行は、私にとって10年ぶりであるが、応募者も8名の少人数ではあったが、皆門中員ということで、実に楽しく、ザックバランに打ち解けた雰囲気であった。
新型コロナの規制が緩和されて海外渡航もある程度、自由に行き来できることは、後期高齢の者にとっては今までの閉塞感からの開放、ストレス解消とか気分転換には一番薬になるとの思いで、喜んで応募したことを覚えている。
今回の主な台湾旅行は、台湾彰化県の同じ梁氏のルーツを持つといわれる人々(中国福建からの渡来のいわゆる漢民族の末裔)で組織する社団法人彰化縣梁姓宗親会への親善訪問ということであったが、その組織自体の設立目的として、先祖の徳を継承し、親孝行と兄弟愛を実践。氏族間の団結を追求し、相互扶助、協力、倫理と道徳を促進する等、おおよそ日本の戦前の道徳教育を彷彿させる定款内容である。
いずれにしても、台湾梁氏一族との夜の交流会(約30人程)では大変な持てなしを受けたが、沖縄の亀島、古謝、國吉、上江洲等の苗字ではなく、オール梁氏の名称であり、国柄からして当然ではあるが、ちょっと違和感があった。ただ、食べたり、飲んだりするうちに彼らの顔つきを良く見ると、我々の顔つきと似ていたのは考えすぎかな。

その中でも宗親会の理事長は、台湾では有数のコンピューター電子周辺機器の製造メーカーの会長として活躍中であり、その統率力とか人柄のよさ等いい印象を持ったのは皆、同じだと思います。

その他、特色ある神社仏閣や台湾原住民の生活等をテーマパークにした九族文化村、世界に誇る国立故宮博物館また超高層ビルで有名な台北101等多くの魅力ある観光名所を見学することができた。今回旅行の現地ガイドさんは、大変な日本びいきで案内先々で日本統治時代にできた多くの施設等の説明では、熱がこもっていた。謝謝。謝謝。

以上で私の台湾旅行の感想等について述べましたが、後期高齢にもなると一人旅ができるわけでもないし、ましてや海外旅行等はお膳立てして貰って、それに乗っかる方法しかないので、今回の久米梁氏呉江会主催の台湾旅行には感謝です。


以上で私の台湾旅行の感想等について述べましたが、後期高齢にもなると一人旅ができるわけでもないし、ましてや海外旅行等はお膳立てして貰って、それに乗っかる方法しかないので、今回の久米梁氏呉江会主催の台湾旅行には感謝です。
今後ともこのような旅行を企画してもらいたいと要望します。以上」

古謝 昇

コロナ明やしが
台湾旅行
肝どんどんすさ
くぬ年なていん
古謝 昇
2024年05月16日
令和6年度春の彼岸祭
去った3月20日門中倶楽部で春の彼岸祭が行われました。会長就任で初の行事主催者となった崎山健伸代表理事を先頭に元祖梁嵩の祭壇に焼香し、参加した理事や祭祀委員全員で礼拝しました。
会長から彼岸祭は年度始めの行事、3月下旬、4月上旬と学事奨励会やシーミー(清明祭)など門中行事が続く、しっかり頑張りたいとの挨拶がありました。
祭壇のお供え物は果物、重箱、白餅それぞれ1対、いつも変わらぬ心のこもったお重は、祭祀委員の方々の力作です。梁氏倶楽部には、祭祀行事の料理をこしらえるための専用の調理準備室があります。祭祀委員メンバーは、ここで和気あいあいと楽しみながら準備します。
礼拝のあとは全員に配られたウサンデーをいただきながら歓談いたしました。久しぶりの行事参加となった梁氏呉江会顧問の國吉保武さん、崎山孝次郎さんもウサンデーを美味しそうにいただいています。

会長から彼岸祭は年度始めの行事、3月下旬、4月上旬と学事奨励会やシーミー(清明祭)など門中行事が続く、しっかり頑張りたいとの挨拶がありました。
祭壇のお供え物は果物、重箱、白餅それぞれ1対、いつも変わらぬ心のこもったお重は、祭祀委員の方々の力作です。梁氏倶楽部には、祭祀行事の料理をこしらえるための専用の調理準備室があります。祭祀委員メンバーは、ここで和気あいあいと楽しみながら準備します。
礼拝のあとは全員に配られたウサンデーをいただきながら歓談いたしました。久しぶりの行事参加となった梁氏呉江会顧問の國吉保武さん、崎山孝次郎さんもウサンデーを美味しそうにいただいています。

挨拶を述べる崎山健伸会長

祭祀委員の皆さん
事務局長 國吉薫
2024年05月14日
台湾彰化縣梁姓宗親会親善訪問報告
令和5年11月、3泊4日の日程で梁氏呉江会会員一行8名が台湾の彰化縣梁姓宗親会との親善交流のため、台湾を訪問しました。呉江会としては、中国福建省の梁氏との交流以外では初の外国訪問となります。親善訪問の報告をさせていただきます。

1. 1日目
1-1「鹿港龍山寺」、「鹿港天妃宮」、「鹿港老街」見学
かつて 台湾 第二の都市だった 鹿港 には、当時の古い 建物 がそのまま残っている。鹿港龍山寺は建物や庭園、内部の装飾など非常に素晴らしく鹿港天后宮は鹿港を象徴する建物、創建は1591年とされ、現存する建物も1936年に建てられた歴史的建造物である。国定古蹟に指定され、台湾各地からの参拝客で賑わっている。
1-2彰化県秀水郷「彰化県梁氏宗親會」訪問 台湾梁氏祖先の碑:清国(1700年代)の時代、大陸から台湾彰化県秀水郷に移住し、開拓をはじめた祖先の畑、3ヘクタールートの地だそうだ。街はずれのその畑の一角に「梁姓、郡祠祀田」と刻まれた石碑が建っていた。大陸から渡来した祖先が、定着発展していった重要な場所の印である。その後梁一族は秀水郷一帯に集落を形成し、発展したようでそこに現存する祖堂に案内された。幾つかある梁族の廟の一つで、有力者の古い祖霊舎が修復され新祖堂として梁族祖先がまつられていた。

少し離れたところに梁一族が管理している道教の寺院らしい立派な建物、「彰化秀水 清龍岩」に案内された。梁徽彬会長はじめとして秀水清龍岩管理委員会の皆さんと面会、挨拶をかわし、焼香、献金して内部を見学した。梁一族を中心に寺院を管理しているが、梁一族の祖先を祭っているところではなく、広く地域の信仰の中心のような寺だった。秀水郷最大で最古の寺院で、農村住民の信仰の中心となっている。中央のホールは観音菩薩を祀り、左のホールは関聖帝を、右のホールは扶余帝が祀つられている。他に玉皇大帝、朱邸千年、蘇邸千年、聖母、大小さまざまな神様が祀られている。清龍岩組織は委員長、副委員長、事務局長、総務グループ、外交グループ財務グループ、祭りグループ、ボランティアグループなどで組み立てられていた。





4-1台北龍山寺見学
1. 1日目
1-1「鹿港龍山寺」、「鹿港天妃宮」、「鹿港老街」見学
かつて 台湾 第二の都市だった 鹿港 には、当時の古い 建物 がそのまま残っている。鹿港龍山寺は建物や庭園、内部の装飾など非常に素晴らしく鹿港天后宮は鹿港を象徴する建物、創建は1591年とされ、現存する建物も1936年に建てられた歴史的建造物である。国定古蹟に指定され、台湾各地からの参拝客で賑わっている。

1-2彰化県秀水郷「彰化県梁氏宗親會」訪問 台湾梁氏祖先の碑:清国(1700年代)の時代、大陸から台湾彰化県秀水郷に移住し、開拓をはじめた祖先の畑、3ヘクタールートの地だそうだ。街はずれのその畑の一角に「梁姓、郡祠祀田」と刻まれた石碑が建っていた。大陸から渡来した祖先が、定着発展していった重要な場所の印である。その後梁一族は秀水郷一帯に集落を形成し、発展したようでそこに現存する祖堂に案内された。幾つかある梁族の廟の一つで、有力者の古い祖霊舎が修復され新祖堂として梁族祖先がまつられていた。

少し離れたところに梁一族が管理している道教の寺院らしい立派な建物、「彰化秀水 清龍岩」に案内された。梁徽彬会長はじめとして秀水清龍岩管理委員会の皆さんと面会、挨拶をかわし、焼香、献金して内部を見学した。梁一族を中心に寺院を管理しているが、梁一族の祖先を祭っているところではなく、広く地域の信仰の中心のような寺だった。秀水郷最大で最古の寺院で、農村住民の信仰の中心となっている。中央のホールは観音菩薩を祀り、左のホールは関聖帝を、右のホールは扶余帝が祀つられている。他に玉皇大帝、朱邸千年、蘇邸千年、聖母、大小さまざまな神様が祀られている。清龍岩組織は委員長、副委員長、事務局長、総務グループ、外交グループ財務グループ、祭りグループ、ボランティアグループなどで組み立てられていた。

「彰化秀水 清龍岩にて記念写真」
なぜ梁一族が主体となって管理しているかは分からなかったが、梁一族が秀水郷で有力な一族であることは推測できる。併設した事務所には梁木川理事長以下約10名の梁の名の付く理事がいて、大きな組織であった。また事務所階下の部屋に、精巧な彫刻が施された清国時代168年前の貴重な神輿が保存されていたが、何の祭りでどのように使われるのか分らなかった。ネットで見た限り近隣のいくつか巡回交流するイベントで引き廻される神輿のようだが、詳細は不明であった。




正式には艋舺龍山寺(ばんかりゅうざんじ)という。本尊は観世音菩薩であるが、現在では道教や儒教など様々な宗教と習合しており、孔子や関帝(関羽、三国志で知られる)、媽祖など、祀られている神は大小合わせて100以上に及ぶ。人々は様々な神が祀られた7つの香炉を順に廻りながら、それぞれの神に参拝する。(参考:Wikipedia)観光客と地元参拝者で賑わっていた。清時代の乾隆3年(173年)、大陸福建省泉州から渡ってきた漢民族の移民たちによって創建され、福建普江安海龍山寺の分霊を迎え入れました。


4-2剥皮寮歴史街区、学校文化施設
剥皮寮歴史街区は龍山寺の近くで、康定路、広州街および昆明街に囲まれたエリア です。「台北市郷土教育センター」は教育と文化を融合し、郷土教育を推進するためリノベーションされたスポットである。剥皮寮とは杉の皮を剥いで様々なもの作っていたことからこの名前がついたそうで、日本統治時代のレンガつくりの建物など残したリノベーション地域、今では台湾アート等の発信基地になっているそうで、観光客と若者でにぎわっていた。

剥皮寮歴史街区は龍山寺の近くで、康定路、広州街および昆明街に囲まれたエリア です。「台北市郷土教育センター」は教育と文化を融合し、郷土教育を推進するためリノベーションされたスポットである。剥皮寮とは杉の皮を剥いで様々なもの作っていたことからこの名前がついたそうで、日本統治時代のレンガつくりの建物など残したリノベーション地域、今では台湾アート等の発信基地になっているそうで、観光客と若者でにぎわっていた。

8.まとめ
「台湾梁氏との交流・親睦深め台湾文化を理解すること」を目的に出張し、以下のように考察した。
今回の台湾梁氏との交流は沖縄梁氏と接点があるのかどうか、重要な関心事であったが、台湾梁氏は約250年前、清国の時代に福建省泉州市安南市あたりから台湾開拓民として移住してきたようであるから、沖縄梁氏とは時代的にも地理的にも接点は少いように思われた。
「台湾梁氏との交流・親睦深め台湾文化を理解すること」を目的に出張し、以下のように考察した。
今回の台湾梁氏との交流は沖縄梁氏と接点があるのかどうか、重要な関心事であったが、台湾梁氏は約250年前、清国の時代に福建省泉州市安南市あたりから台湾開拓民として移住してきたようであるから、沖縄梁氏とは時代的にも地理的にも接点は少いように思われた。
沖縄梁氏は500~600年前、福建省を経由して北京との公的交流をする中で琉球に居住定着している。したがって接点があるにしても、中国福建省の祖先、あるいは700年~800年前の泉州市梁克家あたりまでさかのぼる必要があるかも知れない。今回の交流では細かいルーツの突合せをすることはできなかったが、やっとたどり着いた台湾梁一族なので、まずは顔合わせで懇親を深め、今後交流を重ねる中でルーツや接点が明らかになることを期待したい。さらに地域に根差した台湾梁氏の組織活動も、情報交換して学んでいきたい。
参考:梁傳繼「福興郷元中村田洋仔梁氏前祝公派下祖譜」http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2016/mcps001/index.htm
台湾文化を理解する目的で主な観光地を巡った。台湾は最も近い隣国として、県台北事務所も設置されていて、長い付き合いがある国である。しかし日本の一県としての交流には政治的背景もあって、人的にも経済的にもいま一歩踏み込めないところもあった。また最近ではコロナ禍や台湾有事の緊張感もあって街の雰囲気は気になったが、高層ビルや清潔な街並み、観光客や地元若者たちの賑わい、高速道の車の流れなど、相変わらずの親日的雰囲気は平和的で経済的にも力強さが感じられた。今後も観光を中心とした経済的交流は拡大するだろうし、IT産業やものづくり産業の交流は重要となるだろう。その中で梁氏一族の交流も具体的に活発になることを期待したい。


呉江会副会長 國吉和男
2024年05月13日
令和6年度定時社員総会
2月25日(日)、梁氏倶楽部で令和6年度定時社員総会が開かれました。
國吉克哉会長は、会の冒頭で、昨年度総会で報告したように私、國吉克哉と副会長の國吉和男理事は、今期総会を以って退任する、後任の会長には崎山健伸理事が就任することを先日開催した理事会で決議した。この1年間副会長とともに呉江会の運営に最善を尽くしてきた、会員の御協力、御支援に厚く感謝申し上げるとの挨拶がありました。
事業報告では敬老会は中止となったが清明祭、学事奨励会など基本的事業を例年どおり実施したこと、親子レクリエーション、梁氏美術展を企画して多数の門中関係者が参加、出展したこと、会員参加による訪問団11名が台湾彰化縣梁姓宗親会を訪問して友好交流を行ったこと、また財政面では楚辺空地の駐車場拡張整備工事の完工により、新年度は駐車料収入の大幅増収が見込まれること等が報告され、令和5年度の決算が承認されました。
令和6年度の事業計画では基本的祭祀、行事のほかに美術展や親子レクリエーションは継続事業とし、所有地の活用促進を図り、共有地名義人問題の解決に向けた取組みを一層推進することなどが予算案と共に全会一致で承認されました。
総会審議終了後、会長より先日開催した理事会において、國吉俊秀さん、亀島健司さん、國吉聡志さん、3名の入会が承認されたことが報告されました。
國吉克哉会長は、会の冒頭で、昨年度総会で報告したように私、國吉克哉と副会長の國吉和男理事は、今期総会を以って退任する、後任の会長には崎山健伸理事が就任することを先日開催した理事会で決議した。この1年間副会長とともに呉江会の運営に最善を尽くしてきた、会員の御協力、御支援に厚く感謝申し上げるとの挨拶がありました。
事業報告では敬老会は中止となったが清明祭、学事奨励会など基本的事業を例年どおり実施したこと、親子レクリエーション、梁氏美術展を企画して多数の門中関係者が参加、出展したこと、会員参加による訪問団11名が台湾彰化縣梁姓宗親会を訪問して友好交流を行ったこと、また財政面では楚辺空地の駐車場拡張整備工事の完工により、新年度は駐車料収入の大幅増収が見込まれること等が報告され、令和5年度の決算が承認されました。
令和6年度の事業計画では基本的祭祀、行事のほかに美術展や親子レクリエーションは継続事業とし、所有地の活用促進を図り、共有地名義人問題の解決に向けた取組みを一層推進することなどが予算案と共に全会一致で承認されました。
総会審議終了後、会長より先日開催した理事会において、國吉俊秀さん、亀島健司さん、國吉聡志さん、3名の入会が承認されたことが報告されました。

事務局長 國吉薫
2024年05月13日
令和6年度学事奨励会
3月31日、日曜日、午後1時から令和6年度の学事奨励会が開催されました。午前中大雨となったにも拘わらず、多数の児童生徒、保護者が出席して、門中倶楽部の廊下にも収まらずに玄関口まで保護者が立見するほどでした。
今年の学事奨励会対象者は、幼稚園2人、小学生18人、中学生7人、高校生10人、大学生8人、合計45人です。
奨励金授与の前に、子供たちのためになるお話しを門中であるお二人の方にしてもらいました。一人目は古謝昇さん。二人目が國吉花那さんです。
古謝昇さんはご自身の甥の次男が、プロ野球球団(楽天イーグルス)のドラフト1位指名を受け、入団してプロ野球選手になったお話をされました。ドラフト1位指名を受けるなんてスゴイことです。甥の子供の名前は、古謝樹君。樹君がいかにしてプロ野球選手になる夢を勝ち取ったのか、古謝昇さんは子供たちに熱く語りました。
樹君は少年時代は、体格的にひ弱な子であった。しかし、好きな野球で強くなるために、体力づくりを人一倍励んで努力を重ねた。努力することでは誰にも負けない根性があった。しかし、いくら根性があるからといっても、健康でないと続かない。だから、何事も<努力すること><根性を強く持つこと><健康であること>が大切だ。皆さんも勉強だけが大事と考えるのではなく、スポーツで体も鍛えて、文武両道となるようにと子供たちを激励しました。
二人目は、沖縄県立芸術大学で工芸(染色)を学んでいる國吉花那さんです。花那さんは、スクリーンの映像を見せながら紅型の歴史や紅型の種類、色合いの違い、デザインを紹介しました。紅型の作り方について、型紙を彫ったり(型彫)、型紙を布の上に置いて防染糊を塗ったり(型置)、顔料で布を染めたり(色差)などの工程を、実物の型紙や毛髪を使った刷毛などの用具を子供たちの手に触れさせて説明しました。子供たちはみんな初めて見る紅型用具に興味深く見入っています。
花那さんは、子供たちに、紅型は世界に誇れる染物であること、紅型などすばらしい衣装を生み出した沖縄の文化を大切に守り、継承していきたいと熱く語りました。

講演終了後、学事奨励金、記念品が子供たちに授与されました。みんな嬉しそうです。授与式の最後に、亀島理瑚さん(小学5年)から答礼の挨拶がありました。
「こんにちは。私は今度神原小学校の5年生になる亀島理瑚です。本日は、学事奨励金を頂きありがとうございました。大切に使いたいと思います。お父さんに聞いたところ、私は、梁氏の21世になるそうです。梁氏のことはよくわからないのでこれから勉強したいと思います。ありがとうございました。宜しくお願いします。」
理瑚さん、とても素晴らしい答礼でした。学事奨励会をとおして、子供たちは自らのルーツ、先祖について学んでいきます。
事務局長 國吉薫
今年の学事奨励会対象者は、幼稚園2人、小学生18人、中学生7人、高校生10人、大学生8人、合計45人です。
奨励金授与の前に、子供たちのためになるお話しを門中であるお二人の方にしてもらいました。一人目は古謝昇さん。二人目が國吉花那さんです。
古謝昇さんはご自身の甥の次男が、プロ野球球団(楽天イーグルス)のドラフト1位指名を受け、入団してプロ野球選手になったお話をされました。ドラフト1位指名を受けるなんてスゴイことです。甥の子供の名前は、古謝樹君。樹君がいかにしてプロ野球選手になる夢を勝ち取ったのか、古謝昇さんは子供たちに熱く語りました。
樹君は少年時代は、体格的にひ弱な子であった。しかし、好きな野球で強くなるために、体力づくりを人一倍励んで努力を重ねた。努力することでは誰にも負けない根性があった。しかし、いくら根性があるからといっても、健康でないと続かない。だから、何事も<努力すること><根性を強く持つこと><健康であること>が大切だ。皆さんも勉強だけが大事と考えるのではなく、スポーツで体も鍛えて、文武両道となるようにと子供たちを激励しました。
二人目は、沖縄県立芸術大学で工芸(染色)を学んでいる國吉花那さんです。花那さんは、スクリーンの映像を見せながら紅型の歴史や紅型の種類、色合いの違い、デザインを紹介しました。紅型の作り方について、型紙を彫ったり(型彫)、型紙を布の上に置いて防染糊を塗ったり(型置)、顔料で布を染めたり(色差)などの工程を、実物の型紙や毛髪を使った刷毛などの用具を子供たちの手に触れさせて説明しました。子供たちはみんな初めて見る紅型用具に興味深く見入っています。
花那さんは、子供たちに、紅型は世界に誇れる染物であること、紅型などすばらしい衣装を生み出した沖縄の文化を大切に守り、継承していきたいと熱く語りました。

講演終了後、学事奨励金、記念品が子供たちに授与されました。みんな嬉しそうです。授与式の最後に、亀島理瑚さん(小学5年)から答礼の挨拶がありました。
「こんにちは。私は今度神原小学校の5年生になる亀島理瑚です。本日は、学事奨励金を頂きありがとうございました。大切に使いたいと思います。お父さんに聞いたところ、私は、梁氏の21世になるそうです。梁氏のことはよくわからないのでこれから勉強したいと思います。ありがとうございました。宜しくお願いします。」

理瑚さん、とても素晴らしい答礼でした。学事奨励会をとおして、子供たちは自らのルーツ、先祖について学んでいきます。
事務局長 國吉薫
2024年04月26日
令和5年度秋の彼岸祭
9月23日真夏日となった秋分の日、梁氏倶楽部にて秋の彼岸祭が執り行われました。祭祀委員手作りの重箱と果物を祭壇にお供えし、会長はじめ理事が集まり、みんなでご先祖にお祈りしました。
礼拝後の楽しみは、祭祀委員が腕によりをかけた手作りの赤飯おにぎり入り弁当とウサンデーの食事です。前日の食材買い出しから始まり、当日は早朝から調理に奮闘された委員の皆さん、お疲れさまでした。

礼拝後の楽しみは、祭祀委員が腕によりをかけた手作りの赤飯おにぎり入り弁当とウサンデーの食事です。前日の食材買い出しから始まり、当日は早朝から調理に奮闘された委員の皆さん、お疲れさまでした。

事務局長 國吉薫
2023年05月08日
令和5年度清明祭
コロナ感染予防のため梁氏門中の方々の参加が3年余り中止となっていた清明祭が、4月9日(日曜日)4年ぶりに多くの皆さんの参加のもと開催されました。
参加総数は55名ですが、那覇近郊以外では北谷町、嘉手納町、沖縄市、うるま市など各地から駆け付けた方も多くいました。
清明祭の準備業務は久米梁氏呉江会の祭祀委員が中心となりますが、理事役員も総出で協力して進められました。理事の一人は前日8日にウサンミの食材の一つ、鮮魚(マチ)の買い出しに泊いゆまちに行き、呉江会の料理準備室で大きなシチューマチを30匹余り三枚に下ろします。

また、翌9日は調理されたウサンミ(魚身、鶏肉、豚肉等)を当番の理事達が弁当箱に80食分詰めていきます。お供え物、ウサンミ弁当の用意ができると、運送当番の理事達が車に積み込み、宗家の墓所に運送します。その他、テント、折り畳み椅子、飲み物、氷等は軽トラックで運送します。
荷物が宗家墓所に着くと、墓室前庭にシートを敷き、祭祀委員がお供え物を墓室前に並べ、受付台や飲み物を氷水に浸ける準備が完了すると清明祭の開始となります。
祭式は、はじめに宗家代表亀島伸昭氏と國吉克哉会長が墓右側の「社稷」に、明や清からの作法と言われる三跪九叩頭のしきたりで焼香し、それから中央の墓室に向かい、同じく三跪九叩頭で焼香、拝礼しました。それに倣って全員で拝礼してシーミーが始まりました。

國吉克哉会長の挨拶では、前会長の退任に伴い会長に就任したこと、前会長の功績を引き継いで呉江会をさらに発展させていく所存であること、門中の方々の御協力を今後ともよろしくお願いしたいと挨拶されました。
会長挨拶のあと、事務局長から新任理事及び監事、新会員(社員)、清明祭初参加者の紹介を行いました。
新任理事の吉浜正明さん、新任監事の國吉健郎さんが紹介され、続いて新会員の崎山春樹さん、亀島悌さん、上江洲大樹さん、上江洲渉さん、上津仁さんが紹介されました。

初参加者の吉浜弘二さん 前田一舟さんが紹介され、吉浜弘二さんからは参加記念に泡盛一枡瓶を2本の寄贈がありました。
またうるま市教育委員会の前田一舟さんは、梁氏の伝統祭祀の見学のため、ゲスト参加されました。
続いて國吉和男新副会長の乾杯の音頭とともに、ウサンミ弁当が配布され冷たいビールを飲みながらの懇親会が始まりました。
懇親会の合間に司会より、今期会長及び副会長を退任された國吉保武さんと崎山孝次郎さんが、呉江会の顧問に委嘱されたことが報告されました。
4年ぶりの開催となった梁氏門中清明祭は、久しぶりの再会を喜び近況を語り合う賑やかな懇親会となりました。
ウサンミ


参加総数は55名ですが、那覇近郊以外では北谷町、嘉手納町、沖縄市、うるま市など各地から駆け付けた方も多くいました。
清明祭の準備業務は久米梁氏呉江会の祭祀委員が中心となりますが、理事役員も総出で協力して進められました。理事の一人は前日8日にウサンミの食材の一つ、鮮魚(マチ)の買い出しに泊いゆまちに行き、呉江会の料理準備室で大きなシチューマチを30匹余り三枚に下ろします。


また、翌9日は調理されたウサンミ(魚身、鶏肉、豚肉等)を当番の理事達が弁当箱に80食分詰めていきます。お供え物、ウサンミ弁当の用意ができると、運送当番の理事達が車に積み込み、宗家の墓所に運送します。その他、テント、折り畳み椅子、飲み物、氷等は軽トラックで運送します。
荷物が宗家墓所に着くと、墓室前庭にシートを敷き、祭祀委員がお供え物を墓室前に並べ、受付台や飲み物を氷水に浸ける準備が完了すると清明祭の開始となります。
祭式は、はじめに宗家代表亀島伸昭氏と國吉克哉会長が墓右側の「社稷」に、明や清からの作法と言われる三跪九叩頭のしきたりで焼香し、それから中央の墓室に向かい、同じく三跪九叩頭で焼香、拝礼しました。それに倣って全員で拝礼してシーミーが始まりました。

國吉克哉会長の挨拶では、前会長の退任に伴い会長に就任したこと、前会長の功績を引き継いで呉江会をさらに発展させていく所存であること、門中の方々の御協力を今後ともよろしくお願いしたいと挨拶されました。
会長挨拶のあと、事務局長から新任理事及び監事、新会員(社員)、清明祭初参加者の紹介を行いました。
新任理事の吉浜正明さん、新任監事の國吉健郎さんが紹介され、続いて新会員の崎山春樹さん、亀島悌さん、上江洲大樹さん、上江洲渉さん、上津仁さんが紹介されました。

初参加者の吉浜弘二さん 前田一舟さんが紹介され、吉浜弘二さんからは参加記念に泡盛一枡瓶を2本の寄贈がありました。
またうるま市教育委員会の前田一舟さんは、梁氏の伝統祭祀の見学のため、ゲスト参加されました。
続いて國吉和男新副会長の乾杯の音頭とともに、ウサンミ弁当が配布され冷たいビールを飲みながらの懇親会が始まりました。
懇親会の合間に司会より、今期会長及び副会長を退任された國吉保武さんと崎山孝次郎さんが、呉江会の顧問に委嘱されたことが報告されました。
4年ぶりの開催となった梁氏門中清明祭は、久しぶりの再会を喜び近況を語り合う賑やかな懇親会となりました。
ウサンミ



事務局長 國吉薫
写真 國吉健郎
2023年04月08日
令和5年度学事奨励会
3月26日、日曜日、新型コロナ感染予防のため中止してきた学事奨励会が4年ぶりに開催されました。
今年の学事奨励会対象者は、幼稚園+小学生=17人、中学生+高校生=16人、大学生=11人、合計44人です。当日出席した対象者は33人でしたが幼稚園児、小学生児童の父兄も多数参加されて、廊下まであふれるほどでした。
國吉克哉新会長と宗家代表の亀島伸昭理事が焼香し全員で先租に拝礼して後、会長の挨拶で会が始まりました。
今回特別企画として、野村流古典音楽師範の小渡常雄さんをお招きして古典音楽の紹介と三線を演奏してもらいました。三線の演奏曲は「かぎやで風」。ご高齢にもかかわらず、高音で張りのある声、そして三線の澄んだ高い音色ですばらしい演奏を聞かせてくれました。

お話しでは、遠い昔、皆さんの先祖達が中国から三線や学問道徳(朱子学・儒教)を学び琉球を発展させたこと、琉球では初の学校・明倫堂を建てたように先祖が教育を大事にしたこと、また人の痛みを自分の痛みと思って人を思いやる心、親の恩を忘れないようにという道徳の大事さを子供たちに語りかけました。
♪ ちかさたるがきてぃ ゆだんどぅんすぃるな。
うんみぬふぁや はなぬ にをぃやしらん ♪
訳 近いことを当てにして油断をするな。
梅の葉は花の匂いを知ることはない。
そして古典音楽の本散山節(むとうさんやまぶし)の琉歌を引用して、いつも近ににいる親がいつまでもいると思って油断してはいけない。
梅の花は先に咲き散って後、葉が出るので葉(子)は花(親)のことを知らないと喩えている。皆さんもそうならないように親の言うことをよく聞いて、よく勉強に励み、立派な大人になってくださいと話を締めくくりました。
講演の後、会長から奨励金及び学用品の授与が行われました。

最後は上津敏学事・広報委員長によるハモニカ演奏で、「はとぽっぽ」、「お手てつないで」、「大きな木の下で」などの童謡や卒業式の歌「仰げば尊し」など昔懐かしい曲が披露されました。
今どきの子供達には初めて聞く曲ばかりだったと思いますが、みんな心が暖かくなったようでした。
今年の学事奨励会対象者は、幼稚園+小学生=17人、中学生+高校生=16人、大学生=11人、合計44人です。当日出席した対象者は33人でしたが幼稚園児、小学生児童の父兄も多数参加されて、廊下まであふれるほどでした。
國吉克哉新会長と宗家代表の亀島伸昭理事が焼香し全員で先租に拝礼して後、会長の挨拶で会が始まりました。
今回特別企画として、野村流古典音楽師範の小渡常雄さんをお招きして古典音楽の紹介と三線を演奏してもらいました。三線の演奏曲は「かぎやで風」。ご高齢にもかかわらず、高音で張りのある声、そして三線の澄んだ高い音色ですばらしい演奏を聞かせてくれました。

お話しでは、遠い昔、皆さんの先祖達が中国から三線や学問道徳(朱子学・儒教)を学び琉球を発展させたこと、琉球では初の学校・明倫堂を建てたように先祖が教育を大事にしたこと、また人の痛みを自分の痛みと思って人を思いやる心、親の恩を忘れないようにという道徳の大事さを子供たちに語りかけました。
♪ ちかさたるがきてぃ ゆだんどぅんすぃるな。
うんみぬふぁや はなぬ にをぃやしらん ♪
訳 近いことを当てにして油断をするな。
梅の葉は花の匂いを知ることはない。
そして古典音楽の本散山節(むとうさんやまぶし)の琉歌を引用して、いつも近ににいる親がいつまでもいると思って油断してはいけない。
梅の花は先に咲き散って後、葉が出るので葉(子)は花(親)のことを知らないと喩えている。皆さんもそうならないように親の言うことをよく聞いて、よく勉強に励み、立派な大人になってくださいと話を締めくくりました。
講演の後、会長から奨励金及び学用品の授与が行われました。

最後は上津敏学事・広報委員長によるハモニカ演奏で、「はとぽっぽ」、「お手てつないで」、「大きな木の下で」などの童謡や卒業式の歌「仰げば尊し」など昔懐かしい曲が披露されました。
今どきの子供達には初めて聞く曲ばかりだったと思いますが、みんな心が暖かくなったようでした。
事務局長 國吉薫
写真 國吉健郎
写真 國吉健郎
2023年04月07日
令和5年度春の彼岸祭
午前中は曇り模様だった空もお昼頃には晴れ間が射すようになった3月23日(火)春分の日、梁氏倶楽部で「春の彼岸祭」が挙行されました。
祭礼に入る前に任期満了で退任された崎山孝次郎さん(前副会長)に久米梁氏呉江会の顧問を任命する委嘱状が交付されました。
※ 同じく退任された國吉保武前会長への顧問委嘱状は、本人が当日欠席のため後日交付とした。
今回の彼岸祭には当会の理事・監事の他、千葉県から崎山直樹ご夫妻が参加されました。直樹さんは崎山孝次郎さんの御長男で、千葉大学大学院の准教授として学術研究をされています。直樹さんは、専門分野はヨーロッパの歴史であるが梁氏・クニンダの歴史にも関心があるので、今後は勉強を深めていきたいと挨拶されました。

いよいよ祭礼の始まりです。初めに宗家を代表して亀島伸昭理事と呉江会を代表して國吉和男副会長が元祖梁嵩の祭壇に焼香した後、参加者全員で合掌・拝礼しました。

國吉和男副会長の挨拶の後、祭祀委員(上江洲ハツさん、亀島京子さん)が心を込めて調理したお供え物の重箱料理を皆でいただきます。実際には準備の都合上あらかじめ用意された弁当をウサンデーに見立てていただきます。
ところでウサンデーとは、お供えした物をいただくことですが、お供え物をいただく事で、ご先祖様のご加護が得られるといわれています。
祭壇に供えた重箱にはカマボコ、三枚肉、昆布などのおかずが五品づつ整然と並んでいます。お供えのおかずは、必ず三品・五品・七品などの奇数品目を詰めるものとされています。また、お餅も詰めますが、お餅の個数も奇数です。
なぜ奇数なのでしょうか。これには6世紀頃、中国(唐)から本州、琉球に伝わった陰陽五行の思想が影響しているようです。陰陽五行では、奇数は縁起の良い「陽」、偶数は縁起の悪い「陰」とされていることから、祭祀料理は奇数で揃える風習となったようです。
またお供えのおかずを重箱に詰める作法は、江戸時代後期から明治時代にかけて、薩摩(鹿児島)を通しておせち料理に使われる和食器としての重箱が沖縄に伝わり、沖縄独自の作法として定着したのではないでしょうか。
祭礼に入る前に任期満了で退任された崎山孝次郎さん(前副会長)に久米梁氏呉江会の顧問を任命する委嘱状が交付されました。
※ 同じく退任された國吉保武前会長への顧問委嘱状は、本人が当日欠席のため後日交付とした。
今回の彼岸祭には当会の理事・監事の他、千葉県から崎山直樹ご夫妻が参加されました。直樹さんは崎山孝次郎さんの御長男で、千葉大学大学院の准教授として学術研究をされています。直樹さんは、専門分野はヨーロッパの歴史であるが梁氏・クニンダの歴史にも関心があるので、今後は勉強を深めていきたいと挨拶されました。

いよいよ祭礼の始まりです。初めに宗家を代表して亀島伸昭理事と呉江会を代表して國吉和男副会長が元祖梁嵩の祭壇に焼香した後、参加者全員で合掌・拝礼しました。

國吉和男副会長の挨拶の後、祭祀委員(上江洲ハツさん、亀島京子さん)が心を込めて調理したお供え物の重箱料理を皆でいただきます。実際には準備の都合上あらかじめ用意された弁当をウサンデーに見立てていただきます。
ところでウサンデーとは、お供えした物をいただくことですが、お供え物をいただく事で、ご先祖様のご加護が得られるといわれています。
祭壇に供えた重箱にはカマボコ、三枚肉、昆布などのおかずが五品づつ整然と並んでいます。お供えのおかずは、必ず三品・五品・七品などの奇数品目を詰めるものとされています。また、お餅も詰めますが、お餅の個数も奇数です。
なぜ奇数なのでしょうか。これには6世紀頃、中国(唐)から本州、琉球に伝わった陰陽五行の思想が影響しているようです。陰陽五行では、奇数は縁起の良い「陽」、偶数は縁起の悪い「陰」とされていることから、祭祀料理は奇数で揃える風習となったようです。
またお供えのおかずを重箱に詰める作法は、江戸時代後期から明治時代にかけて、薩摩(鹿児島)を通しておせち料理に使われる和食器としての重箱が沖縄に伝わり、沖縄独自の作法として定着したのではないでしょうか。
事務局長 國吉薫
写真 國吉健郎
写真 國吉健郎