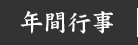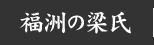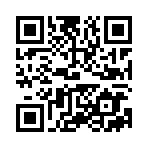2024年12月13日
福州へ行ってきました 1
中国と琉球の交流の歴史については中国・台湾・沖縄の大学で「中琉歴史関係国際学術会議」が組織され研究されています。中国・台湾の大学から研究者が沖縄を訪れる事があり、今年8月には福建師範大学の大学院生一行が梁氏呉江会を訪れています。この逆の話があって、中国人の末裔である久米三十六姓当事者の目線で話を聞かせてくれと、声が掛かり、久米崇聖会の理事長を共に務めた陳氏の仲本さんと僕が、令和6年10月に福建師範大学で久米三十六姓について話をすることになりました。
福建師範大学は福建省の省都福州市にあり県人が福州へ行くと一度は訪れる琉球人墓に近い旗山区に大学があります。学生数5万人、キャンパス内の移動は自転車や車だろうかと心配するほど広大でした。大学にはベトナムやタイなど東南アジアと中国の交流の歴史を研究する研究所があり、その一つに「中琉関係研究所」があって14世紀頃に始まる中国と琉球の交流の歴史、久米三十六姓の事績などの研究拠点となっています。
我々の講演会場は中琉関係研究所のあるビル2階の大教室で、既に70人余が待っていました。研究所所長の頼正維教授をトップに中国琉球の交流史研究者そして大学院や学部の学生達です。そんな会場で話の持ち時間は各1時間半でした。

福建師範大学は福建省の省都福州市にあり県人が福州へ行くと一度は訪れる琉球人墓に近い旗山区に大学があります。学生数5万人、キャンパス内の移動は自転車や車だろうかと心配するほど広大でした。大学にはベトナムやタイなど東南アジアと中国の交流の歴史を研究する研究所があり、その一つに「中琉関係研究所」があって14世紀頃に始まる中国と琉球の交流の歴史、久米三十六姓の事績などの研究拠点となっています。
我々の講演会場は中琉関係研究所のあるビル2階の大教室で、既に70人余が待っていました。研究所所長の頼正維教授をトップに中国琉球の交流史研究者そして大学院や学部の学生達です。そんな会場で話の持ち時間は各1時間半でした。

講演会開催の学内告知(電子版) 頼正維教授へ「梁氏便り」等の資料贈呈
文 國吉 克哉
Posted by たんめー at 13:10│Comments(0)
│その他